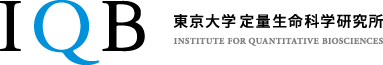定量研インタビュー 川崎 洸司さん
遺伝子発現ダイナミクス研究分野(深谷雄志 准教授)
日本学術振興会特別研究員‐PD
定量研の魅力について教えてください。
自身の研究分野に関連することでは、ゲノムや遺伝子発現調節など、自分の興味のある分野に対して様々な手法や角度から研究に取り組んでいる研究者が身近にいることが魅力的に思います。また、定量研で定期的に開催されるセミナーでは非常に頻繁に海外からのゲストの講演を聴講することができ、国内外で活躍している研究者、研究内容を身近に感じることができます。学生やポスドクがこうした研究者の方々とカジュアルに自分のキャリアパスや日々の悩みなど相談できる機会も用意して貰え、恵まれた環境だと思うので研究者を目指すかどうかに関わらず貴重な体験ができると思います。個人的には、上の世代に独立してラボを持つ研究者が継続的に輩出されていることも自分にとっての目標となり、励みになっていると感じます。


研究テーマについて教えてください
ゲノムDNA中に存在するエンハンサーと呼ばれる配列について研究しています。エンハンサーは遺伝子発現の強さやタイミングを緻密に調節しています。しかし、生きた細胞の中でエンハンサーの機能がどのようにして発揮されているのか、その動作原理は実はよくわかっていません 。自分は、超解像顕微鏡をはじめとした蛍光イメージング手法を駆使することで、生きたショウジョウバエ初期胚の中でエンハンサー活性そのものやエンハンサーと相互作用する転写調節因子の動的なふるまいを高時空間解像度で可視化し、その仕組みを明らかとすることに挑戦しています。
定量研に入る前と後では、定量研の印象はどう変わりましたか
そもそも定量研に入る前にはどういう構成(学生やスタッフの割合、所属など)の研究所なのかもよく分かっていませんでした。入ってみると、附置研究所なこともあってか、学内の特定の学部から院生が進学してくる訳ではないので色々なバックグラウンドの学生がいて面白いなぁと思いました。その分、以前に自分がいた大学のように、「学部時代からの知り合い」のようなものが少なく研究室を越えて横のつながりが生まれにくいように見えるところもありましたが、最近では特に若手PIの方々の主導でHappy Hourなど所内の交流が定期的に行われるようになり、研究室間交流が以前よりも盛んになったように感じます。自分が定量研に入った後からもどんどん変化があるので印象は変わり続けています。

学部時代の学生生活について教えてください
他大学ですが、学部時代には電気・電子系、情報系、生命系の様々な専門科目を学ぶことが出来たので幅広い分野に触れることが出来たと思います。生命系の科目は大学に入ってから初めてちゃんと勉強しました。色々な分野に触れてきたおかげで新しいことに挑戦するときの心理的ハードルが軽減されている気がしますし、良い経験だったなと思います。
研究室選びのアドバイスがありますか
自分は博士後期課程後に研究員として現在の研究室に移ってきたのですが、当時は自分が持っている技術に対してさらにどういう新しいものが増やせそうなのか、を意識して研究室を探していた気がします。月並みですが、その中でも自分が一番夢中になれそうな研究内容の研究室にお話を伺いにいきました。研究にはどうしても膨大な時間を掛ける必要がある時もあると思うので、「もっと知りたい」と自分の中で自然に思えるような内容であることが一番大切な気がします
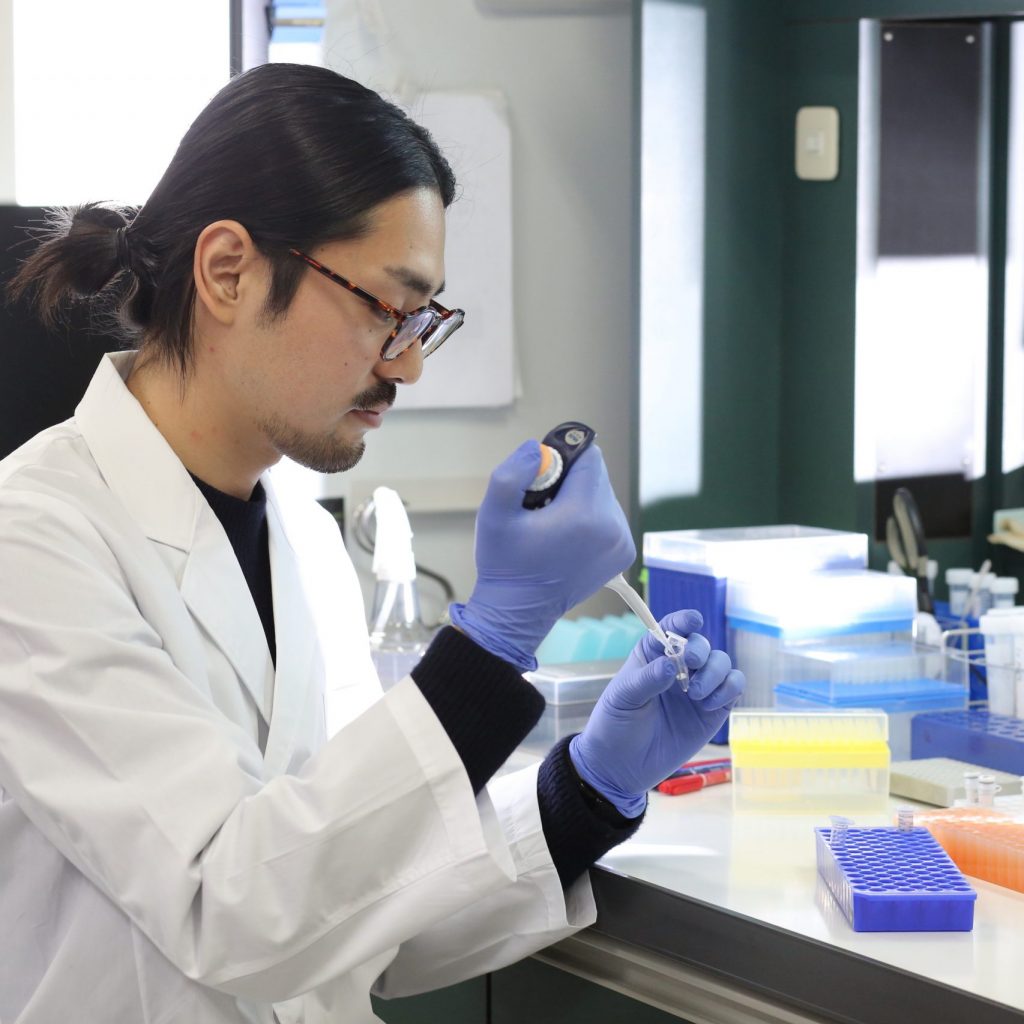
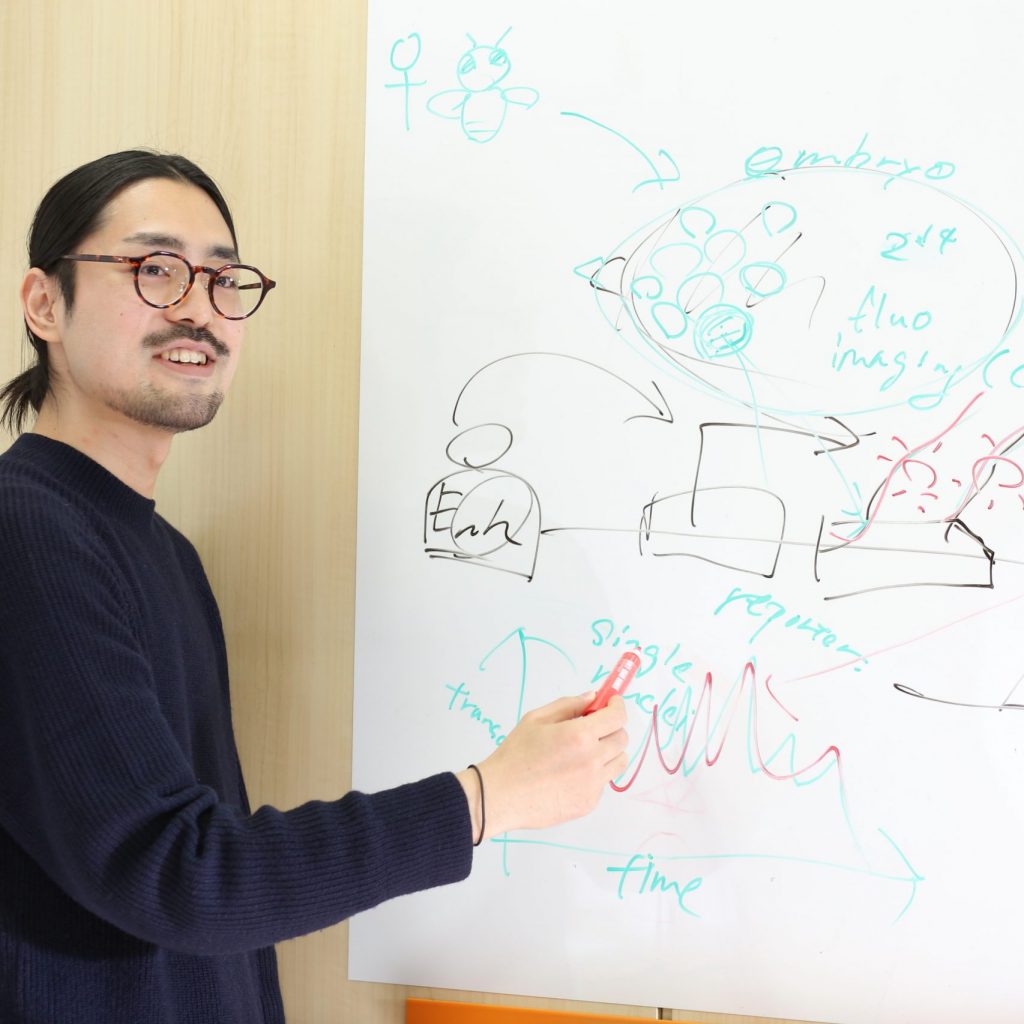
所属している研究室はどのような雰囲気ですか
個人ごとに独立して研究テーマに取り組んでいますが、ラボメンバーの人数が少ないので 一人一人がお互いに密にコミュニケーションがとれている印象があります。ただ、メンバーの移り変わりで(あるいは取り組んでいる実験手法の変化でも)ラボの雰囲気はがらっとすぐに変わると思っているので、もし興味がある研究室がある時は現在のメンバーとなるべくたくさん話をしてみることをおすすめします。
今後の進路や目標はありますか
自分は現在はポスドクですが、 将来的には自分の研究室を主宰して自分の分野を開拓したいと思っています。今の目標は、そこに向けてちょっとずつ努力を積み重ねていくことです。
聞き手:定量研オンキャンパスジョブHP作成チーム
写真撮影:田辺隆三、瀧澤国敏
インタビュー時期:2024年3月