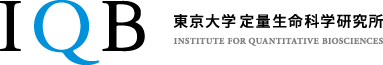定量研インタビュー 薛 世玲那さん
RNA機能研究分野(代表:泊幸秀 教授)
大学院新領域創成科学研究科所属 博士課程
入学して感じる定量研の魅力について教えてください。
異なる分野の一流の研究者の方々がいらっしゃるのはもちろんのこと、学生も多様であることも魅力だと感じています。定量研に所属する研究室の学生は異なる研究科に入学した学生の集まりということもあり、異なるバックグラウンドを持っています。入学当初はコロナ感染症による行動制限真っ只中ということもあり、実感があまりなく、他の研究室の学生はおろか、自分の研究室の学生すら認識が怪しいという状況でした。しかし最近では、学生交流会が開催されるようになり、他の研究室の学生の発表を聞き、コミュニケーションをとる機会が増えたことがとても刺激になっています。

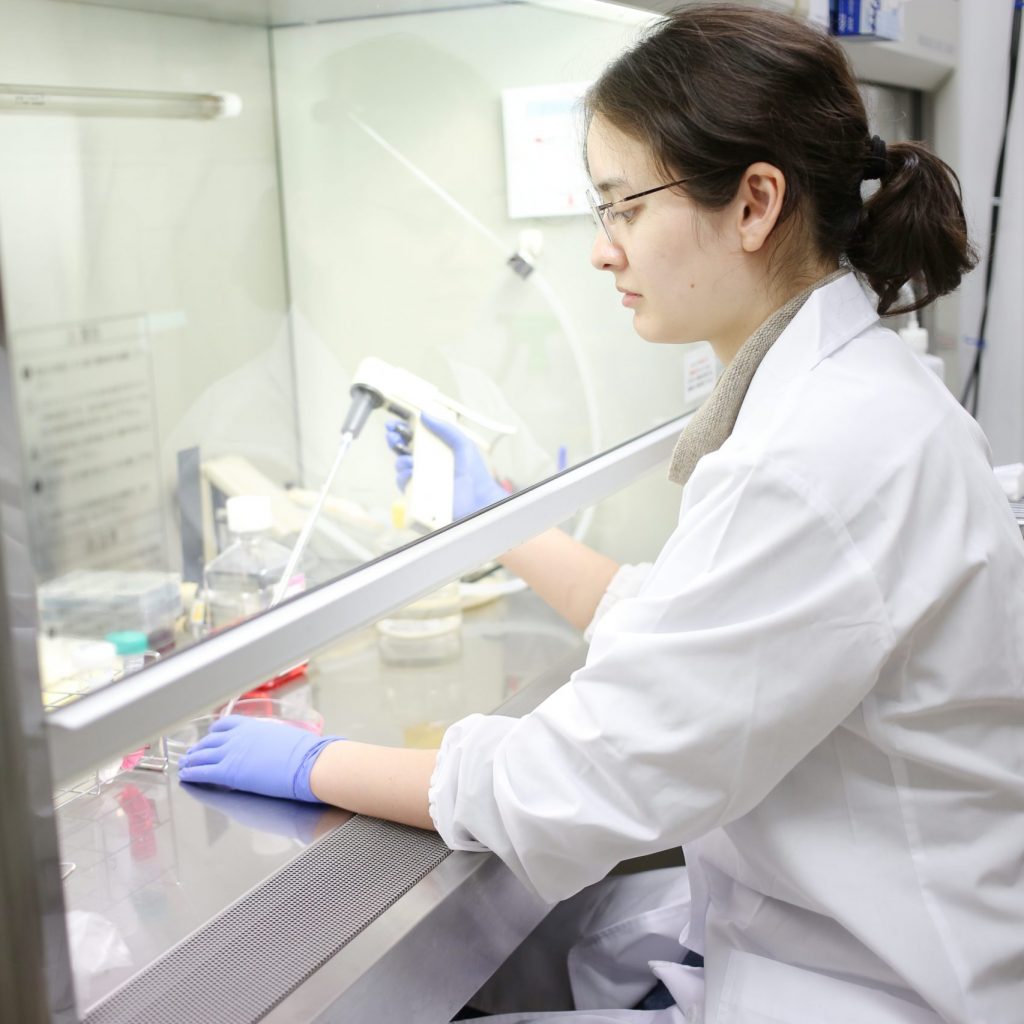
所属している研究室はどのような雰囲気ですか?
RNA機能研究分野という研究室ですが、RNAとその関連だけにとどまらない、異なる手法、バックグラウンドをもった方がいらっしゃるのが特徴的だと思っています。 わからないこと、つまずいたことについてはグループを超えて相談しあえる関係が築けていると思います。 ラボのミーティングでは、スタッフ、学生関係なく活発な議論が行われています。留学生の方も多く所属しています。ミーティングの言語は英語・日本語混合で行っています。
研究テーマについて教えてください。
Heroタンパク質というユニークな種類のタンパク質の研究をしています。Heroタンパク質は全長にわたって特定の構造を持たない超天然変性タンパク質であり、煮沸処理によっても変性・凝集しない性質を持っています。Heroタンパク質はこれまであまり研究が進んでいなかったタンパク質群です。タンパク質は一般に、熱や乾燥、化学的なストレスにさらされると変性、凝集し、機能を失いますが、Heroタンパク質を添加すると、変性・凝集による機能喪失を防げることが所属研究室で明らかになりました。さらにそれらが試験管内だけでなく、細胞内でTDP-43といった神経変性疾患で問題となるタンパク質の異常凝集を抑制できることを明らかにしています。私は、Heroタンパク質が実際にヒト神経細胞で疾患につながるようなタンパク質の異常凝集を抑制できるか、重要なはたらきをもっているのか、神経変性患者由来のiPS細胞から神経細胞を誘導し、疾患病態を再現する実験系を用いて確かめようとしています。共通機器が揃っていることと、異なる分野の専門家がいることが定量研で研究する上での魅力でしょうか。

研究室側では、入学生に対してどのような準備をしていますか?
コロナ禍の始まりと同時の進学だったこともあり、受け入れ研究室もとても苦労されていた印象です。最初の数か月研究室に行くことすら全くできなかったので、実際のデータを用いてRでデータ解析を行う教材をわざわざ準備してくれたりしていました。
入試にはどのような準備をして臨みましたか?
私の時は筆記試験があったので、過去問をひたすら解きました。志望している研究科にどのような専門の先生がいるか調べて、それらの専門にまつわる入門書の一読、the molecular biology of the cellの関連セクションなどの重点的な復習をしました。 どこを受けるにしても提出を求められているところが多かったので、英語については早めにTOEICかTOEFLのスコアを準備するようにしました。
研究室選びのアドバイスをお願いします。
実際に研究室を訪問する、論文を読む、学会に参加することができるのであれば興味がある研究室の発表を聞くといったことでしょうか。正直、実際に入ってみないとわからないことも多いですが、PIの先生をはじめ多くの人に話を聞いてみるのが良いと思います。
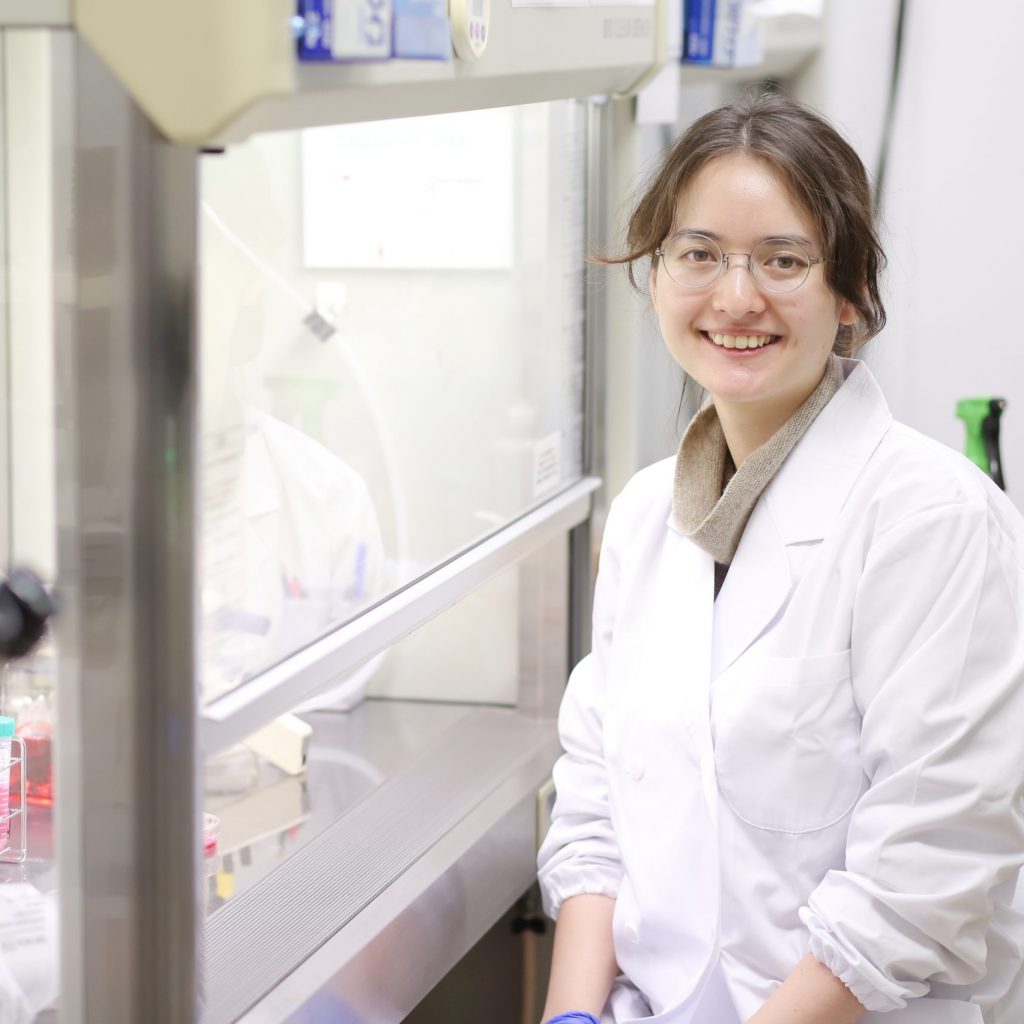

聞き手:定量研オンキャンパスジョブHP作成チーム
写真撮影:田辺隆三、瀧澤国敏
インタビュー時期:2023年2月