徳田 元(Hajime Tokuda)

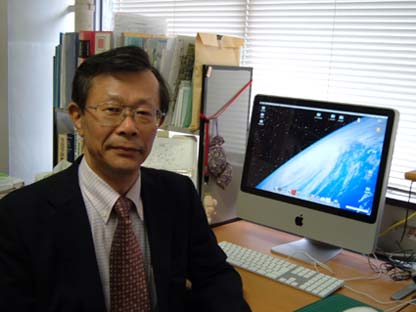
![]()
電子メールのアドレス;htokuda@iam.u-tokyo.ac.jp
TEL;03−5841−7830
FAX;03−5841−8464
![]()
好きな食べ物;肉
好きな動物;カエル(?)
趣味;野球観戦とスキー
 (in ニセコ)
(in ニセコ)
![]()
 日本農芸化学会賞を受賞(206年3月)いたしました。
日本農芸化学会賞を受賞(206年3月)いたしました。
この賞は農芸化学の分野で、学術上または産業上、特に優秀な研究業績をおさめた会員に
授与される賞で、徳田教授の「細菌における蛋白質局在化機構の研究」に対して贈られました。






![]()
インタビュー −教授に聞く− (分生研ニュース第28号より)
聞き手:細胞形成研究分野 博士課程3年 伊東靖子(I)渡辺祥司(W)
―― 先生の学生時代の様子からお聞きしたいのですが。大学生の頃はすごくまじめで、「徳田まじめ君」と呼ばれていたと伺ったのですが。(I)
徳田:それは私が自己紹介で「徳田まじめです」と言ったのです。大学生のときは、いろいろ遊びました。マージャンを徹夜でやりましたし、ビリヤードもやりました。1ゲーム100 円ぐらいで早朝ボーリングもやっていました。
―― では、いつごろから勉強を?(I)
徳田:名古屋大学の大学院を受けるときに必死になって勉強しました。私は推薦入学の資格もありましたが、あまり成績が良くなかったので、そのままだと奨学金がもらえそうになかったのです。試験を受けて成績上位だったら奨学金がもらえるので、必死になって勉強をして、無事に奨学金をもらえました。
―― 学部、修士課程、博士課程と、研究テーマは同じだったのですか?(W)
徳田:全然違いました。学部、修士課程のときは天然物化学をやっていましたから。放線菌が作る抗菌物質や生理活性物質を研究する、伝統のある研究室にいまして、学部生のときは抗ウイルス作用を持つ物質の作用機作を調べていました。ニューカッスルディスィーズ(Newcastle Disease)のウイルスを有精卵に注射して、そこから細胞を取ってきて、そこに生理活性物質をしみ込ませたペーパーディスクを置き、ウイルスの生成を阻害するかどうかというアッセイを4年生のときにしたのです。修士課程では放線菌が作る生理活性物質の構造決定を、精製と結晶化から始めました。そのころちょうど水島昭二先生がウィスコンシン大学の野村眞康先生のところでリボゾームの30S サブユニットの完全再構成に成功して、Nature 誌に論文が出ました。それがすごくインパクトのある研究で、その仕事で水島先生がわれわれの研究室に助教授として赴任されたのです。水島先生が興味を持っていたのは、リボゾームと、当時ほとんど機能がわからなかった膜との関係でした。大腸菌を分画すると、リボゾームは細胞質にあるだけではなく、膜にも必ず一定量結合している。その2つは機能が違うのではないかと考えておられました。それで、私の博士課程でのテーマが、膜結合型リボゾームの機能を明らかにするという仕事になりました。その過程で、リボゾーム生合成の新しいタイプの中間体があるというのがわかりまして、それが博士論文になったのです。
―― 博士号取得後、留学されたのですね。(W)
徳田:われわれの時代は、ポスドクの制度なんてほとんどありませんでしたから、オーバードクターというのが大問題でした。1年間くらい学術振興会の特別研究員をしていたのですが、今ほどいい待遇ではなかったし、次のポジションもありませんでした。ですから、アメリカに出稼ぎに行くような感じで、ニュージャージーのH. Ronald Kabackの研究室にポスドクとして行ったのです。
―― 留学先はどのように決められたのですか。(W)
徳田:博士号を取って特別研究員をやっていたときに「留学したらどうか」と勧められたのです。そのときは、膜関係をやるのが一番いいと思って、留学先を幾つか自分でピックアップしました。その中でもKaback 研からは、割と早くレスポンスがありましたし、Kaback が生化学会で日本に来たときに一度会って、わりといい人だなと思いまして、それで決めました。
―― 当時は膜の機能に関してどこまでわかっていたのですか?(W)
徳田:ノーベル賞を受賞したPeter Mitchell が化学浸透圧説というのを出して、それが正しいがどうかすごい論争があった時期でした。Kaback は、膜を介したプロトン駆動力が存在するという説にずっと反対していました。膜を介した電気化学的ポテンシャル差というのは、生化学者にとっては得体の知れないものだったのです。私もそのころ、留学するに当たっていろいろ勉強していたのですが、Mitchellの理論というのは理解できなかったのです。Kabackが提出したモデルというのは面白くて、呼吸系のコンポーネントの中にラクトースキャリアタンパク質がカップリングするような形であって、その呼吸鎖が動くと、ラクトースキャリアも一緒にコンフォメーション変化をして、基質を結合して輸送するというモデルだったのです。生化学をやっている人間としては、そちらの方が理解しやすかったので、これだったらいいなと思って行ったのです。ところが行ってみると、Kaback は自分の考えを全面的に変えるような時期でした。それは当時、膜電位やΔ pHを測る方法が確立できたことで、バクテリアの膜を介したエネルギー形成に関する理解が格段に進歩したからです。ですから私は一番エキサイティングな時期に加わったわけです。Kaback のところに2年間いて、かなり勉強しました。幾つかの分野に行っても大丈夫かな、こういう背景で仕事をやっていけば何とかなるのではないかな、と漠然と思ったのはそのころです。
―― Kaback 研の次に、イリノイ大学のJordanKonisky 研究室で、かなりいい仕事をされたと伺いましたが?(I)
徳田: Kaback の研究室で知識とテクニックを身に付けたものですから、イリノイに行っても順調に仕事ができました。Konisky 研はコリシンという、エネルギー形成を阻害するタンパク質の作用機構をずっと研究していました。Konisky 研に最初に行ったときに、私は「このメカニズムを一月以内に明らかにしてみせる」と言いました。「そんなことできる訳がない」と学生はみんな笑っていましたが、実際にそのメカニズムを立証するのに一月もかからなかったのです。ちょっと自慢話です。(笑)革新的な技術ができたときに、サイエンスは発展します。エネルギーの形成というのは、見る方法、技術ができて、すごく発展しました。技術の進歩すなわち、新しい情報、すごい情報量の獲得ということです。だから、今われわれがやっている研究でも新しいテクニックが開発できれば格段に進歩すると思います。
―― エネルギー形成を見る最新の技術を持って帰国されて、どんな研究を始められたのですか?(W)
徳田:その後、千葉大学に助手として赴任し、海洋細菌のバイオ・エナジェティクスの研究を始めました。私がしてきた仕事の中で一番好きなのが、この時期にしていた仕事なんです。海洋細菌はナトリウムイオンがないとすぐに溶菌してしまう。それは膜の構造維持に必要だということはわかっていたのですが、なぜ必要かはわかっていなかったのです。ただ、呼吸系の中でナトリウムイオンを特異的に要求する呼吸鎖があるということだけはわかっていました。私はそれが面白いと思ってやり始めたのです。アイソトープを使ってエネルギー形成を見るシステムがあるのですが、アイソトープ実験室にこもってずっと見ていたら、ある晩、予想していたのとは全く違うことが起きたのです。それがナトリウムイオンを排出するということにダイレクトに結びつくデータだったのです。プロトンが排出されるということは、もう常識だったのですが、ナトリウムイオンが排出されるということは、私が初めて発見したのです。そのときはすごく興奮しました。それが自分の研究人生の中でも一番うれしかったときかな。その後、ナトリウム排出性の呼吸鎖というのは千葉大で遺伝子がクローニングされまして、今でもまだ世界中で研究されています。
―― 東大に来られたきっかけは?(W)
徳田:千葉大にいたときに、水島先生が名古屋大学と東大応微研とを兼任されていまして、それで専任になって来てくれということで、応微研に助教授として来ました。当時、水島先生がやっていたのは、タンパク質の膜透過で、UCLA のWilliam Wicknerと競争していたのですが、Wickner も水島先生も、エナジェティクスには弱かったのです。私はKaback のところでバクテリアの細胞質膜を介したエネルギーがどういうメカニズムで形成されて利用されるかを研究していたことで、水島先生に呼ばれたわけです。同じくエナジェティクスがバックグラウンドのArnold J. M. Driessen もWickner のところに行って、エネルギー依存の部分についてどちらもかなり仕事ができたわけです。ただ、Sec(膜透過装置)の再構成系はわれわれのほうが良かったと今でも思っています。各コンポーネントまで分けて、それを全部プロテオリポソームに再構成して、何を入れたら活性が出るのかが初めてわかった訳でしょう。Wickner 達は、膜透過装置を複合体として取ってきて、再構成をやっていましたから、ちょっとはっきりしないなと思ったのですが、お互い間違ってはいませんでした。われわれのグループではSecYとSecE が必要だというのを、まず発表したのですけど、そのときはSecG は入っていなくて、その後、SecY、SecE の活性を上げる因子としてSecG をわれわれが見つけたのです。それで、Wickner が、「ぜひ調べてくれ」と、彼らのサンプルを送ってきたのですが、その中にはちゃんとSecGが入っていました。
―― その頃からリポタンパク質の輸送に関する研究を始められたとお聞きしていますが、リポタンパク質の輸送をする因子を見つけようという人は当時はいたのですか?(W)
徳田:当時いたと思いますよ。Anthony P. Pugsleyの論文なんかを見ると、いっぱいモデルが考えられていたけれど、それをどうやってアプローチすればいいかわからないという状況だったのではないでしょうか。うちはSec を研究していたことで、しっかりとした実験系ができていたことが優位な点でした。松山伸一君がSec の研究をやっていたときにスフェロプラストからいろいろなタンパク質が遊離するけれど、リポタンパク質だけは遊離しないということに目をつけて、彼がずっと温めていたテーマだったのです。その話を聞いて非常に面白いなと思って、どう発展するかと見ていたのですが、そしたら、ペリプラズムからリポタンパク質の遊離因子を見つけて、それからは順調に研究が発展してきました。
―― 今はもうリポタンパク質の輸送は独占企業ですね。(W)
徳田:最初にコンポーネントを見つけて、それを精製して、ミュータントも取っていたから、独走できたのでしょう。ほかのところは、なかなか参入できないでしょうね。ですから、最初にいいシステムをつくるかどうかというのが、独走できるかどうかのポイントで、初め良ければすべてよしという感じです。
―― コンペティターが欲しいとおっしゃってましたが。(W)
徳田:欲しいですね。Sec のときには、非常に切磋琢磨して良かった。研究者同士やりあうときもありましたけれど、お互い尊重しあっていたという面がありましたから。それにその分野がどんどん広がりますね。やっぱり、コンペティターというのは必要だと思いますけど、リポタンパク質にはないですね。
―― 学生に与えるテーマを、どのように決めているのでしょうか?(W)
徳田:リポタンパク質のことをどこまでわかったか、と常に考えています。ただ、ここのところ、テーマが細分化されすぎて少し反省しています。修士論文発表会である程度まとまった話ができないと大変ですから、ついつい細分化されたテーマになる。ただ、そういうテーマを全体でやると、研究室としてはまとまった成果が得らるのですけれども、学生には、ある一部をどうしても受け持ってもらわなければいけない。本当はもうちょっと大きなテーマにしたいのですが、それを学生に出すには、どうなるかわからないような犠牲を強いることになります。そういう先の発展性があるテーマは、スタッフにやってもらいたい。そこから出てきた大きなテーマで、先の見通しがあるテーマを学生にやってもらうことができると思います。
―― 今の学生の研究姿勢に注文はありますか?(I)
徳田:私が自分で実験をやっていたときは、厳密にプロトコルを書いていました。例えば反転膜小胞でも、何年何月何日に調製したかをまず書いて、同じ実験をやるときでも、毎回プロトコルを書き直しました。それに実際に実験をやる前に、バーチャルな実験を何回かやってました。こうすることで、手際がよくなるし、ミスもなくなるように思います。今はみんな大体ぶっつけ本番でやっているのではないですか。
―― 全部が全部ではないですけど、思いつきでやるということは、あまりないですか?(W)
徳田:その前に思いつくように一生懸命考えて、それをプロトコルにして実験していましたよ。実験の途中で思いついたことは、次の実験でやればいいわけで、そのときにやったら駄目です。100 回に1回でも成功して大発見につながればいいですが、あまりうまくいかないのではないでしょうか。
―― これから卒業していく私たちはじめ、分生研の若い研究者に何か、メッセージをお願いします。(I)
徳田:野心的になれ。「ボーイズ・ビー・アンビシャス」を「少年よ大志を抱け」と訳すのは少々きれいすぎるわけで、「野心的になれ」というべきでしょう。安全思考が、ちょっと多いかなという気がします。研究というのはあまり先が見えませんから、ある程度リスキーな部分はどうしてもあると思います。でも研究者の道を選んだら、それを恐れていたら、いい仕事はあまりできないのではないかなと思います。例えば私が留学したときは、いい仕事をしないとポジションを得られないというプレッシャーがあったわけです。プレッシャー無しにいい仕事ができる人はいいのですけれども、普通の人間は、何らかのプレッシャーがないと、いい仕事はできないと思うのです。ですから、「ボーイズ・ビー・アンビシャス」です。
