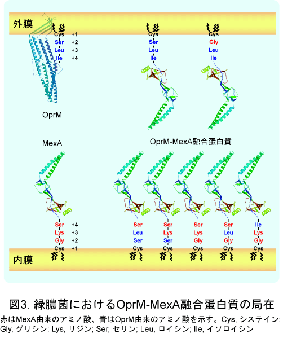「緑膿菌の細胞膜に存在する蛋白質の輸送メカニズムを解明」
1.概要
緑膿菌の細胞表層に結合している膜蛋白質の一種である「リポ蛋白質」の輸送シグナルと、輸送装置であるLol因子を同定しました。Lol因子は輸送シグナルを認識してリポ蛋白質を選別し、指定された場所に運んでいることがわかりました。
2.背景
 細菌リポ蛋白質は脂質で修飾された蛋白質で、脂質を介して細胞膜に結合しています。細菌は様々な種類のリポ蛋白質を発現させて、細胞表層構造の形成、細胞の形態維持、物質輸送、細胞運動、エネルギー生産、情報伝達、宿主細胞への感染など多様な生命活動に用いています。院内感染起因菌として問題視されている緑膿菌は、細胞内に侵入した物質を細胞外に排出する「多剤排出ポンプ」を発現させて様々な抗生物質に対して耐性を獲得しますが、リポ蛋白質は多剤排出ポンプの機能にも必須であることが知られています。
細菌リポ蛋白質は脂質で修飾された蛋白質で、脂質を介して細胞膜に結合しています。細菌は様々な種類のリポ蛋白質を発現させて、細胞表層構造の形成、細胞の形態維持、物質輸送、細胞運動、エネルギー生産、情報伝達、宿主細胞への感染など多様な生命活動に用いています。院内感染起因菌として問題視されている緑膿菌は、細胞内に侵入した物質を細胞外に排出する「多剤排出ポンプ」を発現させて様々な抗生物質に対して耐性を獲得しますが、リポ蛋白質は多剤排出ポンプの機能にも必須であることが知られています。
リポ蛋白質はグラム陰性細菌では内膜または外膜に結合しています。細菌ではすべての蛋白質は細胞質で合成されるため、リポ蛋白質が機能を発揮するためには、合成された後に所定の場所まで輸送される必要があります。このためにリポ蛋白質は輸送シグナルを持っていて、輸送装置がそのシグナルを認識してそれぞれのリポ蛋白質を正しい場所に運びます。大腸菌ではリポ蛋白質のアミノ末端の次(+2位)がアスパラギン酸であれば内膜にとどまり、アスパラギン酸以外であれば外膜に輸送されます。これはリポ蛋白質輸送の「+2ルール」と呼ばれています。また、私達の研究により、Lol因子と呼ばれる蛋白質が+2ルールに従って大腸菌リポ蛋白質を内膜と外膜に選別して輸送していることもわかっています。
ところが、近年のゲノム解析の進展にともない、大腸菌以外のグラム陰性細菌には+2位にアスパラギン酸を持たない内膜リポ蛋白質が存在することが明らかになってきました。今回私達は、緑膿菌の多剤排出ポンプを構成する内膜リポ蛋白質MexAの+2位がグリシンであることに注目し、緑膿菌リポ蛋白質の輸送シグナルと輸送装置の研究を行いました。
実験方法と結果:MexAが内膜に局在化するために必要な領域を特定するため、MexAと外膜リポ蛋白質OprMの融合蛋白質を段階的に作製し、それぞれのリポ蛋白質が内膜・外膜のどちらに局在化するかを解析した結果、緑膿菌では+2位ではなく+3, +4位のリジン、セリンの2つのアミノ酸がリポ蛋白質の内膜局在化に重要であることがわかりました。次に緑膿菌リポ蛋白質の輸送装置を特定するために、緑膿菌のLol因子(LolAおよびLolCDE)を精製し、リポ蛋白質の輸送を試験管内で観察しました。LolCDEをリポ蛋白質とともにプロテオリポソームに再構成し、LolAを添加したところ、リポ蛋白質はプロテオリポソームから遊離しました。これに対して、+3, +4位をリジン、セリンに置換したリポ蛋白質はプロテオリポソームから遊離しませんでした。一方、大腸菌のLolCDEを用いると、+3位, +4位にリジン、セリンを持つリポ蛋白質もプロテオリポソームから遊離しました。これらの結果から、緑膿菌においてもLol因子によってリポ蛋白質が外膜に局在化すること、およびLolCDEがリポ蛋白質の選別に直接関わっていることがわかりました。Lol因子による輸送機構は細菌種を通じて共通していると予想しています。
図をClickして下さい。
大きく
なります。


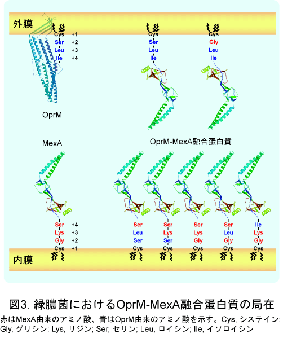
3.今後の展望
リポ蛋白質は様々な細胞機能を担うことが明らかになっていますが、多くのリポ蛋白質の機能は未だわかっていません。リポ蛋白質が内膜、外膜のどちらに局在するかは、その機能を予測する上で重要な情報になります。これまでリポ蛋白質の局在場所の予測は+2ルールに基づいてされてきましたが、今回の解析結果は従来の+2ルールが普遍的な選別ルールになり得ないことを示すものです。リポ蛋白質の局在場所の予測は新たなルールに従って再検討する必要が出てきました。今回、緑膿菌ではリポ蛋白質が新たな「+3, +4ルール」に基づいて選別されることが明らかになりましたが、まだルールの全貌を解明するには到ってません。選別ルールを完全に理解し、すべてのリポ蛋白質の局在場所を高い確度で予測できるように、リポ蛋白質とLol因子の相互作用機構を分子レベルで解析するとともに、緑膿菌リポ蛋白質の+3位、+4位のアミノ酸を系統的・網羅的に置換して、それぞれの局在場所を確定する研究を進めています。
グラム陰性細菌の外膜には生育に必須のリポ蛋白質が存在することが知られています。これらのリポ蛋白質や、輸送装置であるLol因子は抗生物質のターゲットとして新たな感染症治療薬の開発に役立つと期待されます。また、リポ蛋白質の輸送を阻害すると多剤排出ポンプの機能を阻害できるため、多剤耐性菌に対して既存の抗生物質を再び使用できるようになる可能性があります。
発表雑誌
本研究は5月4日号のThe Journal of Biological Chemistryに2報の論文として掲載されました。
1.成田新一郎、徳田元. Amino acids at positions 3 and 4 determine the membrane specificity of Pseudomonas aeruginosa lipoproteins. The Journal of Biological Chemistry, Vol. 282, Issue 18, 13372-13378, May 4, 2007
2.田中慎哉、成田新一郎、徳田元. Characterization of the Pseudomonas aeruginosa Lol system as a lipoprotein sorting mechanism. The Journal of Biological Chemistry, Vol. 282, Issue 18, 13379-13384, May 4, 2007
用語解説
●グラム陰性細菌
細菌は細胞表層の構造の違いによってグラム陽性と陰性の2つのグループに大別されます。グラム陽性細菌は細胞質膜の外側にペプチドグリカン層を持つのに対し、グラム陰性細菌は更にその外側に外膜を持っています。細胞質膜(内膜)と外膜に挟まれた空間はペリプラズム空間と呼ばれます。外膜に局在する蛋白質は細胞質で合成された後、内膜とペリプラズム空間を通過して外膜まで輸送されます。
●細菌リポ蛋白質
動物の血漿中に存在するリポ蛋白質とは異なり、細菌のリポ蛋白質はアミノ末端のシステインが脂質と共有結合した蛋白質で、脂質部分を介して細胞膜に結合しています。リポ蛋白質は細胞質で前駆体として合成された後、内膜を透過し、そこで脂質が結合した成熟体となります。外膜に局在するリポ蛋白質は、さらにLol因子の作用で内膜から遊離してペリプラズム空間を横断し、外膜に組み込まれます。
●プロテオリポソーム
人工的に作製した脂質膜の小胞に蛋白質を配向させたもので、様々な蛋白質の機能を試験管内で解析するために用いられます。私達はLol因子によってリポ蛋白質が内膜から遊離する反応をプロテオリポソームを用いて解析しています。プロテオリポソームを用いることにより、リポ蛋白質の遊離反応に必要な因子を特定できるほか、エネルギー依存性などを分子レベルで解析することができます。
 細菌リポ蛋白質は脂質で修飾された蛋白質で、脂質を介して細胞膜に結合しています。細菌は様々な種類のリポ蛋白質を発現させて、細胞表層構造の形成、細胞の形態維持、物質輸送、細胞運動、エネルギー生産、情報伝達、宿主細胞への感染など多様な生命活動に用いています。院内感染起因菌として問題視されている緑膿菌は、細胞内に侵入した物質を細胞外に排出する「多剤排出ポンプ」を発現させて様々な抗生物質に対して耐性を獲得しますが、リポ蛋白質は多剤排出ポンプの機能にも必須であることが知られています。
細菌リポ蛋白質は脂質で修飾された蛋白質で、脂質を介して細胞膜に結合しています。細菌は様々な種類のリポ蛋白質を発現させて、細胞表層構造の形成、細胞の形態維持、物質輸送、細胞運動、エネルギー生産、情報伝達、宿主細胞への感染など多様な生命活動に用いています。院内感染起因菌として問題視されている緑膿菌は、細胞内に侵入した物質を細胞外に排出する「多剤排出ポンプ」を発現させて様々な抗生物質に対して耐性を獲得しますが、リポ蛋白質は多剤排出ポンプの機能にも必須であることが知られています。